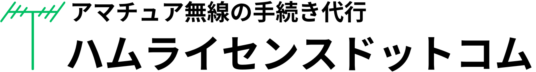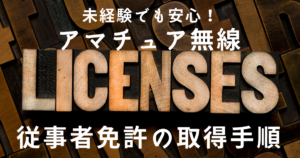アマチュア無線技士資格の種類完全ガイド - 初心者からベテランまでの4つの資格区分
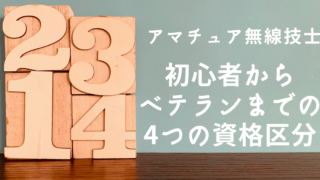
アマチュア無線を始めようと考えている方にとって、最初の関門となるのが無線従事者免許の取得です。
この記事では、アマチュア無線技士の4つの資格区分について、それぞれの特徴や違いを分かりやすく解説していきます。
無線従事者免許とは?
無線従事者免許は、電波法に基づいて総務大臣が付与する国家資格です。
無線従事者資格には、無線レーダや業務無線、放送局などを開設・管理運用するために必要な「プロの資格」と、私たちのように趣味で無線を運用するための「アマチュアの資格」があり、アマチュア無線局を開設して運用するためには、原則としてアマチュア無線技士の資格が必要です。
アマチュア無線技士の資格は、難易度に応じて4つの級に分かれており、上位の資格ほど、より高度な無線設備の運用が可能になります。
4つの資格区分の概要
第四級アマチュア無線技士
- 難易度: ★☆☆☆
- 対象: 初心者、入門者向け
- 国家試験: 法規(12問)と無線工学(12問)の2科目
- 養成課程講習会
- 運用可能な周波数帯: 8MHz以下および21MHz帯以上で、モールス符号によるものを除く
- 出力制限: 10W以下(8MHz以下又は21MHzから30MHzまで)、20W以下(30MHzを超える周波数)
初めてアマチュア無線に触れる方におすすめの入門資格です。比較的易しい試験内容で、ハンディトランシーバーや車載トランシーバーなどを使い基礎的な無線通信を楽しむことができます。趣味でFPVドローンを使う際にも、最低でも第四級アマチュア無線技士の免許が必要です。
第三級アマチュア無線技士
- 難易度: ★★☆☆
- 対象: 基礎知識とモールス符号を身につけた方
- 国家試験試験: 法規(16問)と無線工学(14問)の2科目
- 養成課程講習会・Eラーニングでの取得も可能です。
- 運用可能な周波数帯: 8MHz以下および18MHz帯以上
- 出力制限: 50W以下
モールス符号を使用した電信の運用が可能になり、使用できる周波数帯・出力も増えるため、本格的な交信を楽しみたい方に適しています。HF(短波)帯のモールス通信を使えば、海外交信も十分に可能です。
第二級アマチュア無線技士
- 難易度: ★★★☆
- 対象: 中級者向け
- 国家試験: 法規(30問)と無線工学(25問)の2科目
- 養成課程講習会・eラーニングでの取得も可能です。
- 運用可能な周波数帯: 全ての周波数帯
- 出力制限: 200W以下
高出力での運用が可能となり、DX通信(遠距離交信)など、より高度な無線運用を楽しむことができます。日本のアマチュアでは、一級と二級に限定されている「DX通信のメインストリート」と呼ばれる14MHz帯と、10MHz帯が使用できるようになります。
第一級アマチュア無線技士
- 難易度: ★★★★
- 対象: 上級者向け
- 国家試験: 法規(30問)と無線工学(30問)の2科目
講習会は実施されておらず、取得には国家試験を受験することが必要です。
- 運用可能な周波数帯: 全ての周波数帯
- 出力制限: なし(免許が下りるのは1,000W以下)
最高峰の資格であり、全ての周波数帯で高出力での運用が可能です。専門的な知識と技術が必要とされます。
資格選びのポイント
- 運用目的の明確化
- 趣味として楽しむレベルなら第四級や第三級
- DX通信を目指すなら、モールス通信が使える第三級以上
- DXコンテストで上位を目指すなら第一級
- 学習時間の目安(独学で国家試験を受験する場合)
- 第四級:1ヶ月程度(過去問題集の丸暗記)
- 第三級:1~2ヶ月程度(過去問題集の丸暗記+モールス符号の暗記)
- 第二級:3〜5ヶ月程度(過去問の理解と演習)
- 第一級:6ヶ月程度(過去問の理解と演習)
よくある質問
Q1: 資格の飛び級は可能ですか?
A1: はい、可能です。必要な知識さえあれば、いきなり上位の資格を取得することもできます。
Q2: 下位の資格は上位の資格があれば必要ないですか?
A2: その通りです。上位の資格があれば、下位の資格で可能な運用はすべて行うことができます。
Q3: 試験はいつ受験できますか?
A3: 第三級・第四級アマチュア無線技士の試験は、全国300か所以上の会場(パソコン教室のことが多いです)でCBT方式(コンピュータによる試験)により、随時実施されています。
第一級・第二級アマチュア無線技士の試験は年3回(4月、8月、12月)、東京都、札幌市、仙台市、長野市、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、松山市、熊本市及び那覇市の試験場で実施されています。
Q4:試験以外での取得方法はありますか?
A4:eラーニングや、講習会で取得できます。国家試験に比べ、短い時間で効率的な学習ができることが特長です。
Q5:資格を取る前にアマチュア無線の運用を体験することはできますか?
A5:体験運用の制度を活用すると、免許がなくても無線交信を体験できます。ハムイベントや、地域の科学館などのイベントで体験できる機会があります。
まとめ
アマチュア無線従事者資格は、自身の目的や経験レベルに応じて選択することができます。
初めての方は第四級から始めて、徐々にステップアップしていくことをおすすめします。
資格取得には、独学で国家試験に合格して取得する方法と、講習会やeラーニングを受講し、修了試験に合格して取得する方法があります。